「リスティング広告を始めたいけど、よく分からない」
「リスティング広告っていくらから始められるのだろう」
このような悩みを持っている人も多いのではないでしょうか。
広告を用いるのであれば、できる限り費用対効果が高く自分に合っているものを選びたいですよね。リスティング広告はWeb広告の中で最も主流な広告の1つで、多くの方に利用価値があります。
そこで、本記事ではリスティング広告の基本的な内容や利用するメリットなどを解説していきます。
本記事で分かる内容は以下の通りです。
- なぜリスティング広告がWeb広告の中で人気なのか
- リスティング広告はいくらから始められるのか
- リスティング広告とSEOの違い
リスティング広告とは、検索結果に表示される広告
リスティング広告とはGoogleやYahoo!の検索結果に表示される広告です。ユーザーが検索した特定のキーワードに対して広告を出稿できます。
例えばGoogleで「東京 リフォーム」と検索すると、検索結果の上部と下部に都内のリフォーム会社の広告が表示されていることが分かるでしょう。どのキーワードに対して広告を出稿するのかは、広告主が決められます。
リスティング広告は正確には、「検索連動型広告」と「ディスプレイ広告」の2つに分類されますが、基本的には「リスティング広告=検索連動型広告」と表記されることが多いです。
本記事でも「検索連動型広告」のことをリスティング広告と表現する点をあらかじめご了承ください。
リスティング広告のメリット4選
冒頭でも説明したように、リスティング広告はWeb広告の中で最も主流な広告の1つです。リスティング広告を用いるメリットは以下の4つが挙げられます。
- 購買意欲が高いユーザーに広告を表示できる
- ターゲティングを行える
- 少ない予算でも始められる
- 広告の改善がしやすい
それぞれ具体的に説明していきます。
メリット1:購買意欲が高いユーザーに広告を表示できる
冒頭でも説明したように、リスティング広告は自分で決めた特定のキーワードに対して広告を出稿できます。
つまり、より購買意欲の高いユーザーに絞って広告を出稿できるわけです。例えば、都内で戸建てのリフォーム会社を営んでいる場合について想定してみましょう。
このケースの場合、以下のようなキーワードで検索するユーザーはリフォームの意欲が高いと想定できます。
- 都内 リフォーム 戸建て
- 東京 一軒家 リフォーム
つまりこのようなキーワードに対して広告を出稿すれば、「リフォームを申し込んでくれる可能性が高いユーザー」に限定して広告を表示できるわけです。
逆に、下記のようなキーワードに対しては広告を出稿するメリットは少ないことが予想されます。
- 都内 リフォーム マンション
- 沖縄 リフォーム
どのようなキーワードが自社に適しているのかを見極め、不要なキーワードに配信しないことがリスティング広告の成功の秘訣とも言えるでしょう。
メリット2:ターゲティングを行える
リスティング広告は特定のキーワードのみに広告を表示できるだけでなく、特定のユーザーに対してのみ広告を表示させることも可能です。これを、ユーザー属性のターゲティングと言います。
ターゲティングができるユーザー属性の例は以下の通りです。
- 年齢や性別
- 地域
- 使用デバイス(PCやスマホなど)
- 曜日や時間
細かくターゲティングを行うことによってより費用対効果が高くなることが期待できます。例えば、都内のリフォームを行っているのであれば地域を「東京都」に限定できるわけです。
都内のリフォームに限定しているのであれば、沖縄のユーザーに広告をする意味はありませんよね。もし広告が表示されてクリックされてしまえば、無駄なコストが発生してしまいます。
あらかじめ分かっている項目についてはターゲティングを行い、分からない項目については実際に運用を開始してから調整していきましょう。
注意点として、最初から絞りすぎるのはおすすめできません。リスティング広告を実際に運用してみれば分かると思いますが、予想外のユーザーがターゲットになることもあります。
予算にある程度余裕があるのであれば、実際に配信してみてから細かくターゲティングを行うのがおすすめです。
メリット3:少ない予算でも始められる
リスティング広告は最低1,000円からスタートでき、「どの程度リスティング広告に費用をかけるか」の予算も自分で決められます。
広告媒体などによっては予算調整が難しい場合も多々あるでしょう。例えば、テレビCMなどは最低でも数百万円必要なケースが大半です。
リスティング広告は少ない金額で始められる上に、月によって予算の調整なども容易にできます。例えば、「今月は30万円をリスティング広告に使ったけど、来月は10万円にしたい」と思ったら、すぐに変更できるわけです。
ただ、少ない予算で運用しても効果が出ないケースもある点には注意してください。1,000円から始められますが、実際に効果的に運用するためには最低でも5万円程度は必要となります。
メリット4:広告の改善がしやすい
リスティング広告の結果はリアルタイムですぐに確認できるため、改善がしやすいのが特徴です。逆に言うと改善ありきの広告ですので、改善が最も重要となる点はあらかじめ理解しておきましょう。
リスティング広告では、広告全体の結果が見れるだけではなく、キーワード別の結果も把握できます。先ほどと同様に、都内で戸建てのリフォーム会社を営んでいるケースを想定してみましょう。
以下のキーワードに対して広告を出稿したとします。
- 「都内 リフォーム 戸建て」
- 「都内 リフォーム 3階建て」
- 「都内 リフォーム おしゃれ」
それぞれのキーワードに対して分析をした結果、「都内 リフォーム 3階建て」のキーワードの結果が思わしくありませんでした。
このケースの場合、「都内 リフォーム 3階建て」のキーワードのみ広告を止めることも可能ですし、改善した上で続けることもできるわけです。
細かく結果が分かることによって、必要なキーワードだけ残して不要なものを削除・改善することができます。
リスティング広告のデメリット3選
続いて、リスティング広告のデメリットについて解説していきます。リスティング広告のデメリットは以下の3つが挙げられます。
- 認知やイメージ浸透には向かない
- 運用コストがかかる
- 専用のLPが必要なケースがある
それぞれ具体的に説明していきます。
デメリット1:認知やイメージ浸透には向かない
リスティング広告はテキストのみの広告ですので、訴求ポイントが多くはありません。画像や動画の方が、商品やサービスに対してイメージが付きやすいのは言うまでもないと思います。
つまりリスティング広告は商品の認知やブランドイメージの定着を目的としている場合には効果が少ないです。
Web広告の中でも画像や動画を用いて視覚的に訴求できる広告も多々あります。冒頭で説明した「ディスプレイ広告」も画像や動画を用いて広告を出稿できるため、商品の認知やイメージ浸透には効果的だと言えるでしょう。
ディスプレイ広告について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
関連記事:ディスプレイ広告とは?メリットやリスティングとの違いも解説!
デメリット2:運用コストがかかる
リスティング広告には広告費の他に、運用していくための人件費も必要になります。特にWebマーケターがいない会社は注意が必要です。
リスティング広告の運用には専門的な知識が必要な上に、日々の改善が必要不可欠です。社内にWebマーケターがいない場合は、運用に時間がかかってしまうケースも多いでしょう。
社内にリスティング広告を運用できそうな人材がいない場合には、代理店に頼んだり、Webマーケティング支援の会社に依頼したりするのもおすすめです。
自社で人材が確保できなさそうであれば、ぜひ検討してみてください。
デメリット3:専用のLPが必要なケースがある
リスティング広告を運用する際に効果的な手法の1つが「広告専用にLP(ランディングページ)を作成する」です。ここでのLPとは、広告から流入してきたターゲット専用のWebページを作成することを意味しています。
しかも、場合によっては広告のキーワード別にLPを複数作成している企業も少なくありません。ただ、LPを作るのには非常に手間がかかります。
専用のLPを作成する理由は、広告から流入してきたターゲットに適した訴求をすることが可能となり、結果的にCVR(コンバージョン率)の向上が期待できる点です。
商材によっては今のWebサイトをそのまま利用できる場合もあるかと思いますが、できれば専用のLPを作る方がより費用対効果が高くなる場合が多いと思います。
リスティング広告の費用
リスティング広告は広告が表示されただけで費用が発生するわけではなく、あくまでクリックされた場合に費用が発生する「クリック課金制」です。
1回のクリックで発生する費用のことをCPC(クリック単価)と言います。CPCはキーワードごとに異なり、競合が多いキーワードは高くなる点を理解しておきましょう。
CPCは安いキーワードであれば100円弱、高いキーワードであれば1,000程度と幅があります。最低でも1クリック100円程度かかる場合が多いため、粗利が100円未満で薄利多売の商売を行っている場合にはリスティング広告は向きません。
リスティング広告を用いる場合には、ある程度の粗利が出る商材である必要があるわけです。実際に広告を出稿したいキーワードのCPCはキーワードプランナーにて調べられます。
リスティング広告の順位が決まる仕組み
検索キーワードによりますが、リスティング広告は3個〜4個程度表示されます。当然ですが、上位に表示されるほどクリック率は高くなるため、できるだけ上位に表示されたいですよね。
リスティング広告の順位は、「広告ランク」と呼ばれるものによって決定されます。広告ランクは「品質スコア × 入札価格」で算出されたランクです。以下簡単に用語の解説をします。
- 品質スコア:広告の品質を表すスコアで、キーワード・広告文・クリック率などの要素を元に1〜10で表されます。
- 入札価格:広告主が決定する「いくらまで払えるのか」の価格
つまり、極論「品質スコア」が低かったとしても入札価格を高く設定すれば上位に表示されるわけです。
ただ、費用対効果はできるだけ高い方が良いと思います。したがってリスティング広告ではいかに品質スコアを高くするのかが重要になってくるわけです。
リスティング広告と自然検索(SEO)どちらを始めるべき?
リスティング広告と自然検索(SEO)の2つは比較されることが多いです。自然検索とは、リスティング広告以外の検索結果の部分のことを意味しています。
自然検索で表示されるWebページの順位は、ユーザーが検索したキーワードに最も適したページの順番です。
この自然検索で上位を目指すのがSEOで、以下のようなメリットが存在しています。
- ユーザーがページをクリックしても、費用が発生しない
- 一度上位に表示されると、一定期間は上位のままである可能性が高い
ただ、SEOは費用をかけたり努力したりすれば必ず結果が出るわけではありません。また、一度作成したページの順位が確定するまでには数ヶ月かかる場合もあります。
結果が出るまでに時間がかかる上に、結果の不確実性がデメリットとして挙げられるわけです。
したがって、どちらを始めるのかについては以下を参考にしてみてください。
- 結果が早く欲しい→リスティング広告
- 時間がかかったとしてもコストのかからない流入経路が欲しい→SEO
社内の人材や予算に限りがある場合にはどちらも並行して進めていくのがおすすめです。ただ、現状そのような会社は多くないと思います。
ご自身の状況に合わせて最適な方を選んでみてください。
まとめ
リスティング広告は自社の求めるターゲットに対してピンポイントに広告を表示できるため、費用対効果が高い広告の1つです。
少額から始められる上に予算の調整も容易にできるため、「何かWeb広告を始めたい」と思っている方は始めるべきです。
他のWeb広告についても知りたい方は下記の記事をご覧ください。
関連記事:Web広告の種類と特徴を徹底解説!
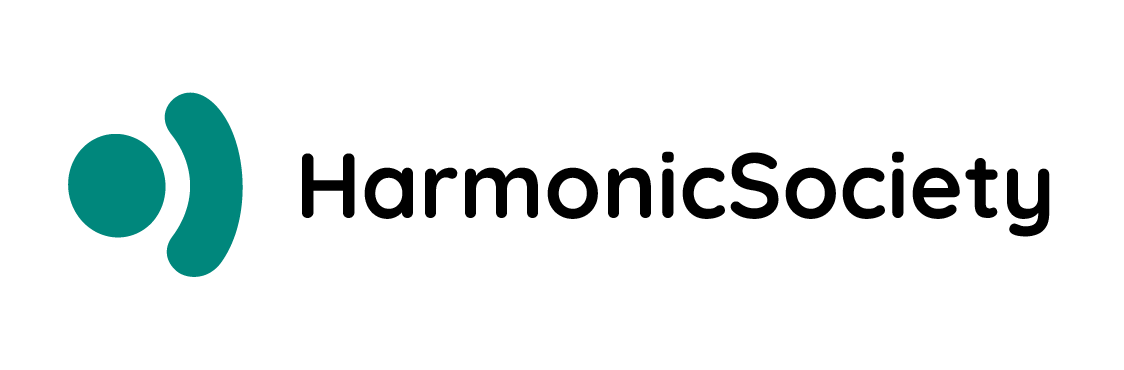


.jpg)






