費用対効果とは、費用に対してどのくらいの利益(効果)を得られたのかを示す指標です。
コンテンツマーケティングを内製化する場合、自社の人材、お金、時間を投入してコンテンツを作成します。そのため、費用対効果の計算方法や考え方を身につけることが経営戦略の最適化につながるでしょう。
本記事では、コンテンツマーケティングにおける費用と効果の捉え方を解説した上で、費用対効果の計算方法と計算例についてまとめました。
費用対効果を高める方法やコンテンツマーケティングを途中で挫折しないコツも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください
<目次>
- コンテンツマーケティングの費用対効果はわかりにくい?
- 費用対効果の計算例
- コンテンツマーケティングの費用対効果を高める方法
- コンテンツマーケティングを途中で挫折しないために
- コンテンツマーケティングの費用対効果を高めたいならHarmonic Societyにご相談を
関連記事:初心者にもわかりやすく!コンテンツマーケティングとは?成功のためのポイント解説
コンテンツマーケティングの費用対効果はわかりにくい?
コンテンツマーケティングは、見込み顧客に有益なコンテンツを配信して信頼関係を醸成し、最終的な売上につなげるマーケティング戦略です。コンテンツのテーマや配信方法を自社が自由に決められるため、商品・サービスの認知拡大や企業ブランディングにも活用できます。
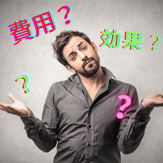 しかし、どのくらい商品の認知が高まったのか、企業イメージが向上したのかといった効果は数値で表しにくく、費用対効果がわかりにくいと感じる方も多いのです。
しかし、どのくらい商品の認知が高まったのか、企業イメージが向上したのかといった効果は数値で表しにくく、費用対効果がわかりにくいと感じる方も多いのです。
そもそも費用対効果を測定する目的は、企業にとって「最も効率的に利益を生み出す施策を見つけ出すこと」です。商材に対して効果的な戦略を見つけ出し、経営戦略を最適化させます。
そのためコンテンツマーケティングの費用対効果を測定する場合も、費用と効果に正しい項目を設定する必要があります。正確な費用対効果を測定して、適切な施策を選択するのです。
コンテンツマーケティングの費用
コンテンツマーケティングの費用は、運営する企業や手法によって異なりますが、必ず発生します。
一般的には、HTMLなどのWeb専門知識がない方でも簡単にWebサイトのコンテンツ作成・更新・運営ができるシステム(CMS)を活用することが多いでしょう。
| コンテンツマーケティングにCMSを活用する場合の費用内訳(例) |
| ・CMS導入費用 |
| ・サーバー代 |
| ・ドメイン費用 |
| ・コンテンツ制作費用(社内人件費用を含む) |
サイトの新規設計から取り組む場合は、サイトのデザインや設計にもプラスで費用がかかります。 また、制作を外注する場合には、制作会社側に制作費を払います。
コンテンツマーケティングはWebサイト以外にも、SNSの運用やホワイトペーパーの作成、プレスリリースの発行などさまざまあります。何を制作するかによっても費用は異なります。
コンテンツマーケティングの効果
費用対効果は、「費用対効果=利益(効果)÷費用」で表せますが、コンテンツマーケティングでは、販売戦略によって計算式が異なります。
例えば、Web上で商品・サービスを直接購入してもらう場合の計算式は「売上=販売単価×個数」です。 顧客との取引期間が売上に直結するサブスクリプション型サービスの場合は「顧客のLTV×顧客数」で算出できます。
見込み顧客の新規獲得が目的ならば、問い合わせや資料請求の獲得がコンバージョンにあたるでしょう。「コンバージョン1件あたりの価値×獲得数」によって、コンテンツマーケティングの効果を測定できます。コンバージョンの価値の計算方法は後述します。
関連記事:LTV(ライフタイムバリュー)とは?計算方法や売上を最大化するテクニック
費用対効果の計算例
費用対効果を計算する際は、何を指標にするかによって計算式が異なります。ここでは3つのケースに沿って計算例を解説します。利益を指標にする場合
利益を指標にする場合は、ROIの算出方法を運用できます。
ROIは、投資した額に対しどれくらいの収益があったかを示す指標であり、英語の「Return On Investment」からきています。日本語では「投資収益率」「投資利益率」と訳されます。
| ROIの計算式。 |
| ROI = 利益 ÷ 投資金額 × 100 (%) |
投資金額は、施策にかかった費用のことです。
ここでは、300万円の売上が発生したA商材を例にしてみましょう。
⦅ A商材の費用対効果を計算するために必要なデータ(例)⦆
・A商材の売上=300万円
・コンテンツマーケティング費用①(CMS利用料、サーバー代などの運用費)=30万円
・コンテンツマーケティング費用②(コンテンツ作成代)=30万円
・コンテンツマーケティング費用③(人件費用など)=20万円
利益は(売上-費用)で算出しますので、計算例では売上からコンテンツマーケティング費用①②③を差し引きします。
売上 300万円 − (30+30+20)= 220万円
| ROIの計算式にあてはめたものがこちら。 |
| ROI = 220万 ÷ 80万 × 100% = 275% |
A商材のROIは275%と算出できました。
「利益」と「費用」にどの数値を使うかによって、算出される%は変わってきます。また、ROIが100%の状態では、投資額と同じ額の利益が出ているという事になり効率が悪いと言えます。100以上で投資効果が高いと考えられます。
問い合わせや資料請求を指標にする場合
新規の見込み顧客を獲得したい場合に指標となるのが、問い合わせ数や資料請求の数です。
まずは成約1件あたりの売上から逆算して、問い合わせや資料請求の「効果」を算出。続けてコンテンツマーケティングにかかった費用を加味することで費用対効果を算出できます。
| 問い合わせを指標にする場合の計算 |
| 1. 問い合わせ獲得の効果を金額に換算する=費用対効果の「効果」 |
| 2. コンテンツマーケティングにかかった費用を出す=費用対効果の「費用」 |
| 3.効果から費用を差し引く |
例として、売上が50万円のB商材を、Webサイトを運用して販売したとしましょう。
⦅ B商材の費用対効果を計算するために必要なデータ(例)⦆
・B商材の売上=50万円
・コンテンツマーケティング費用 = 30万円
・見積もりから発注に至る確率 = 20%
・資料請求から見積もりに至る確率 = 10%
まずは見積もり1件の価値を算出しましょう。
(見積もり1件の価値=成約金額×見積もりから発注に至る確率) 計算式:50万円×0.2=10万円
見積もり1件の価値は10万円となりました。
続けて資料請求1件の価値を算出しましょう。(資料請求1件の価値=見積もりの価値×資料請求から見積もりに至る確率) 計算式=10万円×0.1=1万円
見積もり1件の価値が1万円だとわかりました。
もしも見積もりを20件獲得できたなら、費用対効果はどうなるでしょうか。20万円(1万円×20)-30万円=-10万円
投資した費用は30万円ですので、見積もり20件の獲得では赤字となってしまいます。
では、40件獲得できていたらどうでしょうか。40万円(1万円×40)-30万円=10万円
見積もりを40件獲得できていたら黒字となります。
上記はあくまで一例です。企業の商材や選択する手法によって、別の項目を設定する必要があるでしょう。
SNSやPV(ページビュー)を指標にする場合
商品・サービスの認知拡大や、企業ブランディングを指標とする場合、それらは数値で測りにくく何を成果と定めるのか問題となります。
この場合には、KGI(経営目標達成指標)やKPI(重要目標達成指標)を設定して、達成状況を判断していく方法がおすすめです。
PV数やSNSのユーザー獲得数などの項目を、自社の商材や顧客の特徴に合わせて設定しましょう。
関連記事:KGI・KPIとは?違い・設定する意味・具体例を解説
コンテンツマーケティングの費用対効果を高める方法
費用対効果を高めるには、見込み顧客に有益なコンテンツを配信する必要があります。ポイントを3つ解説します。
プロジェクトに一貫性を持たせる
コンテンツマーケティングで目標を達成させるには、まず「在り方」を統一させる必要があります。
 コンテンツマーケティングの施策は、LP、メルマガ、ホワイトペーパー、ブログ記事や動画、SNS、オフラインのセミナーやイベントなどさまざまな種類があります。
コンテンツマーケティングの施策は、LP、メルマガ、ホワイトペーパー、ブログ記事や動画、SNS、オフラインのセミナーやイベントなどさまざまな種類があります。
どの施策に力を入れるのか、どのような戦略でゴールを目指すのかを明確にし、プロジェクトにおける社内の認識を統一します。
また、コンテンツごとで方向性が変わってしまってはいけません。同じペルソナを見据えて、一貫性のあるコンテンツ制作をおこないます。
ターゲットとなるペルソナと、カスタマージャーニーマップの作成が必要になるため、見込み顧客に有益なコンテンツを制作できるはずです。
関連記事:ペルソナの作り方を具体的に解説!メリットや注意点も紹介
関連記事:カスタマージャーニーマップの作り方。メリットや注意点も合わせて解説
コンテンツを蓄積して評価を向上させる
自社のメディアにコンテンツを蓄積させて、見込み顧客と検索エンジンからの評価を高めましょう。
 両者から高評価されることで検索ページで上位表示されやすくなり、コンバージョンの増加につながります。 コンバージョンの増加は、費用対効果を高めます。
両者から高評価されることで検索ページで上位表示されやすくなり、コンバージョンの増加につながります。 コンバージョンの増加は、費用対効果を高めます。
オウンドメディアにブログ記事を配信する場合は、毎週2本から3本以上の記事を投稿するのがおすすめです。
更新間隔が空き過ぎると顧客離れがおきる可能性がありますので、一定のサイクルで投稿しましょう。
PDCAサイクルを回してコンテンツの質を高める
 費用対効果を高めるためには、コンテンツの量だけでなく質も重要。コンテンツが蓄積されてきたら、定期的にコンテンツを評価・改善して、より見込み顧客に有益な内容に仕上げていきましょう。
費用対効果を高めるためには、コンテンツの量だけでなく質も重要。コンテンツが蓄積されてきたら、定期的にコンテンツを評価・改善して、より見込み顧客に有益な内容に仕上げていきましょう。
古くなった数値を新しくしたり、最新情報を付け加えたりすることで、検索順位を大幅に高められる可能性があります。
コンテンツマーケティングを途中で挫折しないために
コンテンツマーケティングでかかった初期費用を回収して、継続的な成果を出していくために、注意したいポイントを解説します。短期間で成果を出そうと焦らない
コンテンツマーケティングは、多くの人手や時間が必要になります。コンテンツが充実してくるまでには一定の期間が必要です。
 短期間で成果を出そうと焦ると、誤った方法を選択してしまうかもしれません。例えば、コンテンツの質を無視して量産だけを目的に記事を大量発注する方法です。
短期間で成果を出そうと焦ると、誤った方法を選択してしまうかもしれません。例えば、コンテンツの質を無視して量産だけを目的に記事を大量発注する方法です。
大量発注する場合、記事の品質管理がむずかしくなります。その結果、方向性や品質がバラバラのコンテンツが量産されてしまい、メディアの評価が停滞するおそれがあるのです。
コンテンツマーケティングはじっくりと腰を据えて取り組んでいきましょう。
外注を上手に利用する
コンテンツマーケティングの運用が軌道に乗ると、初期費用を回収して継続的な利益を生み出してくれます。しかし運用初期は、費用対効果が一番悪い時期のため「このままで大丈夫だろうか……」と、先行きに不安を感じるかもしれません。
 そこでおすすめしたい方法が、コンテンツ制作会社の活用です。
そこでおすすめしたい方法が、コンテンツ制作会社の活用です。
自社の課題や、予算状況に合ったプランを提示してくれる会社に依頼すれば、貴重なリソースを節約しながら十分な成果を見込めます。
携わったスタッフには、コンテンツマーケティングを運用した知見や経験も手に入るでしょう。外注を利用する場合は、複数の会社から見積りをとって、費用対効果を高めてください。
関連記事:コンテンツマーケティングを外注するメリットとは?選定のコツも解説
コンテンツマーケティングの費用対効果を高めたいならHarmonic Societyにご相談を
コンテンツマーケティングの費用対効果を正しく計算するためには、運用目的を再確認して「費用」と「効果」を正しく設定しましょう。コンテンツマーケティングの計算式は、設定した指標によって異なりますので間違わないようにご注意ください。
しかしリソースなどが問題となり、コンテンツマーケティングの費用対効果を高めるのがむずかしい場合もあると思います。
その場合はコンテンツ制作サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
 Harmonic Society株式会社の伴走型サービス「Gengoka」は、200名以上への取材で培った傾聴力を生かしたヒアリングで、お客様の希望にあったコンテンツを作成いたします。
Harmonic Society株式会社の伴走型サービス「Gengoka」は、200名以上への取材で培った傾聴力を生かしたヒアリングで、お客様の希望にあったコンテンツを作成いたします。
Gengokaのディレクターは、BtoB商材を扱う大手外資系コンサルティングの出身です。BtoB商材のコンバージョン達成を通して企業の利益拡大をサポートします。
ぜひこの機会に以下の「経営の悩み、言葉で解決します。」をクリックして、伴走型サービス「Gengoka」の概要をご確認ください。
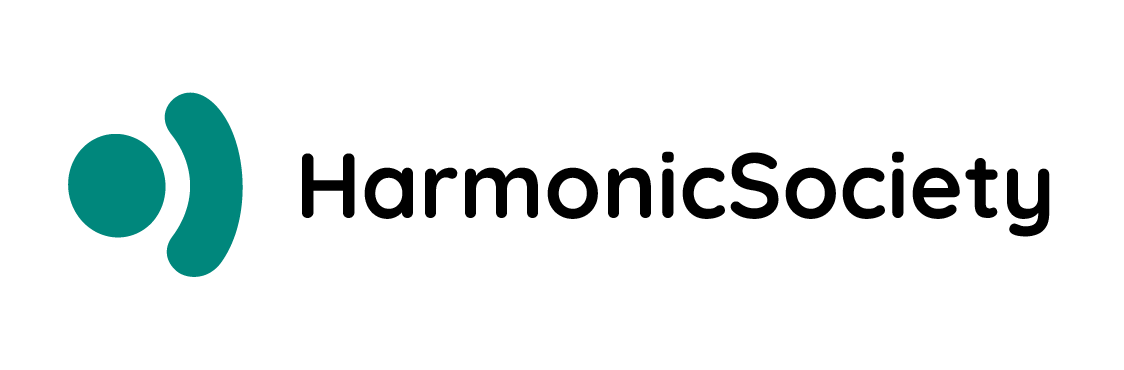


.jpg)






