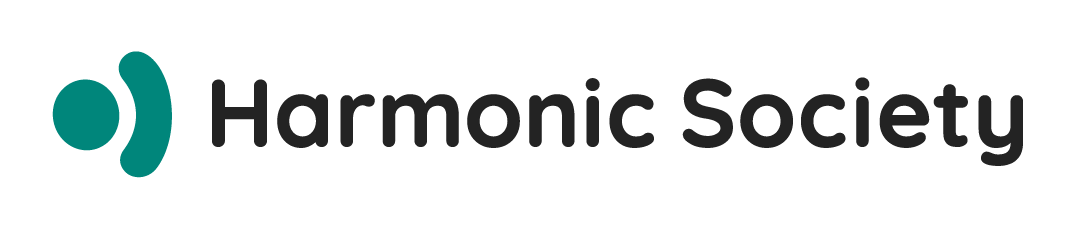「オムニチャネルとはどういったことなのか?」そのように思うことはありませんか?
小売業では、顧客があらゆるチャネルを自由に行き来する「オムニチャネル」が注目されています。買い物方法と受け渡し方が複数用意され、希望する場所で商品を受け取ることができる。多様な選択肢から、自分の都合・好みで選べる買い物体験ができることが特徴です。
本記事では、オムニチャネルとは何か、注目される理由やオムニチャネルの本質をわかりやすく解説します。
オムニチャネルとは、顧客があらゆるチャネルを自由に行き来する仕組み
オムニチャネルとは、顧客があらゆるチャネルを自由に行き来する仕組みのことです。オンラインチャネル(Webサイト)やオフラインチャネル(店舗)、モバイルチャネル(スマートフォンなど)といった複数のチャネルを統合し、顧客体験を向上させることを目標としています。
オムニチャネルは、企業が顧客から最も高い満足を得るために必要なものを提供するという観点から考えられており、顧客体験を改善し、消費者を惹きつけるための新しいアプローチとなります。
企業が消費者に正しい情報を提供し、その情報を消費者が見つけやすい形で提供することで、顧客体験を改善します。
これまでのチャネル形態の変遷
オムニチャネルを理解する上で、これまでのチャネル形態の変遷について解説します。
マーケティングにおけるチャネル論は「顧客から自社ブランドへの愛顧を獲得するために、チャネルをどのように統制するのか」という視点から研究されてきました。
過去のチャネル論から登場した分類をその定義を時系列で紹介します。
シングルチャネル
「シングルチャネル」の理解はシンプルです。
店舗を1つだけ持つ手法で、顧客も商品も販促も、全てが1つしか存在しない店舗を軸に統制されています。
商店街によく見られるような、個人商店主による店舗を思い浮かべるとわかりやすいです。
マルチチャネル
次に「マルチチャネル」とは、文字通り商品やサービスを扱う店舗を複数持つ手法です。
例えばご当地の有名食材を扱う店舗が、お取り寄せ用にオンライン店舗も展開している状況を想像してください。
地域の顧客には実店舗で販売し、遠方の顧客にはオンライン店舗で販売します。
この場合、統制すべき接点は複数になりますが、同一顧客が地域の実店舗と、お取り寄せ用のオンライン店舗の両方を併用することは想定していない状況です。
それぞれの店舗は対象とする顧客が違う状態となるため、店舗ごとに顧客・商品・販促を管理する必要があります。
クロスチャネル
「マルチチャネル」対して「クロスチャネル」は、同じ顧客が使い分けられる店舗を複合的に提供する手法です。
例えば同一の顧客が、週末は近所のスーパーのオフライン店舗で買い物し、忙しい平日はそのスーパーのオンライン店舗をモバイルから使用する状況を想像すると分かりやすくなります。
ただしクロスチャネルでは、統制する軸はあくまでも店舗にあるため、各店舗が顧客・商品・販促を管理しています。
そのため同じ顧客がオンライン店舗とオフライン店舗で買い物をしていたとしても、店舗側はそれが把握できません。
オムニチャネル
「クロスチャネル」に対して、ネットとリアルの融合をさらに進め、店舗を横断して顧客を管理するのが「オムニチャネル」です。
オムニチャネルという言葉は、最近では一般的な経済誌などでも目にするようになりました。
デジタルマーケティングに関わる人間には、数年前から聞き慣れたバズワードですが、その取り組みが一般的なビジネスパーソンの耳にも入るようになってきたのは、つい最近のことです。
昨今ではセブン&アイ・ホールディングスを筆頭に、多くの流通小売業でオムニチャネル戦略の立案、構築、実行が声高に叫ばれ、それがようやく形になりつつあります。
またその成否についても、各所で論じられるようになってきました。
オムニチャネルが実現すると、顧客はオンライン店舗にいてもオフライン店舗にいても企業側から正しく「顧客」として認識され、統一された対応を受けられることになります。
オムニチャネルは、「すべてのチャネルを統合し、消費者にシームレスなショッピング体験を提供するマーケティング手法」です。
現在のチャネル論においては、このオムニチャネルの状態が、進化の最先端とされています。
「オムニチャネル」の本質は顧客行動の進化
オムニチャネルは「企業視点でのチャネル進化プロセス」の中に位置付けられるように見えます。
しかしその変化の内容を見ると、シングルチャネルからクロスチャネルに至る過程と、クロスチャネルからオムニチャネルへの過程では大きな違いがあります。
本章では、オムニチャネルの本質について解説します。
変化したのは「店舗」ではなく「顧客管理」
シングルチャネルからクロスチャネルまでは、店舗が1つから複数へ、顧客ごとの複数店舗から1人の顧客への複数店舗へと、顧客接点の形態が変化していています。
それに対して、クロスチャネルとオムニチャネルでは顧客接点である店舗は何も変化していません。
変化したのは店舗ではなく、顧客管理です。
つまりシングルチャネルからクロスチャネルまでは「店舗を軸に顧客の管理を行っている」のに対して、オムニチャネルからは「顧客を軸にチャネルの管理を行う」ことになります。
これまでのオフライン企業は、店舗によって、その流通機能のすべてを束ねてきました。
顧客管理はもちろん、例えば立地に即した店舗ごとの商品の仕入、在庫管理、値付け、情報の発信や販促など、店舗ごとに最適な形を追求してきたと言えます。
しかし「顧客を軸にチャネルを管理する」となると、すべてが変わってしまいます。
顧客属性の把握を全社的な観点から行い、顧客の買い物行動に合せて最適なチャネルを再編し、仕入れや在庫管理、さらには値付けや情報発信から販促まで、すべての店舗を横断し顧客ごとに統制する必要が出てくるからです。
課題は「店舗の効率的な運用」から、まさに「顧客へのシームレスなショッピング体験の提供」に変化します。
この課題に対応するためには、顧客を軸として、オフライン店舗とオンライン店舗に横串を通す体制が必要になります。
すなわちオムニチャネルとは、小売業にとって、店舗基点から顧客基点への経営変革であると言えます。
チャネルの主導権は顧客に移った
オムニチャネルに対応しなければらないのはなぜでしょうか?
それは、「顧客の買い物行動がオムニチャネル化している」からです。
その背景にはスマートフォンの普及があります。
スマートフォンがあれば、あらゆる場所であらゆる情報にアクセスし、あらゆる店舗を選択し、あらゆるものを購入できるようになります。
そうなれば、1つの店舗で選択から購入までを完結させる必要はなくなります。
例えば家電量販店の店頭で商品を試しながら価格コムで価格や評価情報を探索し、アマゾンで購入することも顧客の選択次第です。
来店したからといって、そこでの情報だけを信じるわけはなく、そこで購入するとも限りません。
すなわち、オムニチャネルの本質とは、企業側の進化ではなく、顧客の買い物行動の変化にあります。
自社がオムニチャネルに対応しなければ、顧客は自分の買い物行動に合った他社を選択するだけです。
「チャネルの主導権が顧客に移った」という前提を、忘れないようにしましょう。
すべての「接点」がチャネルである
顧客を軸にしてチャネルを統制するという見地に立つと、もう1つ大きな変化が起きます。
それは、「チャネル=店舗」ではなく、店舗はチャネルの1つに過ぎなくなるということです。
「チャネル=顧客とのあらゆる接点」と捉える必要が出てきます。
これまでは、良い立地に良い店舗を出せば、顧客は店舗に足を運んでくれました。
企業側も、店舗が顧客の選択から購入までの流通機能を統合するという前提に立っているため、統制すべきチャネルとは、店舗のことでした。
しかし、顧客を軸にしてみれば、いまや買い物行動は店舗だけでは完結しません。
仮に自社の店舗で購入するにしても、選択の多くはネットとモバイル端末からの情報によって行われます。
「オムニチャネル時代の小売業は、モバイルデバイスを活用した情報を中心としたコンシェルジュモデルへと移行する」と言われています。
顧客を軸にチャネルを統制するのであれば、来店前の情報チャネルや、購入した後の接点も含めて考える必要があります。
店舗はもはや、顧客の買い物行動における、1つの通過点に過ぎません。
顧客の選択に影響を与える、店舗・アプリ・商品・メディア・SNS、そのすべてが情報であり、チャネルであると考えねばならないのです。
顧客の買い物行動を軸として、これらのチャネルを配置・連動させるという視点が必要になります。
ここまで、オムニチャネルという考え方の登場の背景、そして「顧客を軸としたチャネル管理」へとパラダイムがシフトしていることをチャネル形態の変遷に沿って見てきました。
すでに、チャネルの主導権は顧客に移っています。だからこそ、チャネルとは店舗ではなく、顧客とのあらゆる接点を対象としなければいけません。
そして競争の焦点は、オンラインとオフラインにチャネルを置くこと自体ではなく、それによってどんな購買体験を提供できるかに移っています。
オムニチャネル化する顧客を捉えるポイント3つ
本章では、顧客に独自の購買体験を提供するために、個々の企業がどのような視点でチャネルを設計すればよいか3つのポイントを解説します。
単にチャネルオンからオフへ、オフからオンへと移行させることに価値はありません。
顧客基点に立ち、提供する購買体験を思い描き、その実現のために自社が強みを持つチャネルを組み合わせることが求められます。
そのような取り組みを進める企業こそが、顧客とのつながりを創り、強めることができるはずです。
オムニチャネル化する顧客を捉える要点は、「時間」「空間」「連携」の3つです
「顧客時間」に寄り添う
1つ目の要点は、「時間」です。
時間とは、顧客の買い物行動における、「選択→購入→使用」のプロセスです。
これまでのチャネル設計では、「購入」という瞬間を最も重視し、これをゴールとする傾向が強くありました。
しかし、これまで述べてきた通り、チャネルの主導権は顧客に移っているため、顧客の買い物行動全体で見れば、購入はゴールではなく通過点に過ぎません。
したがって、購入という「点」だけを見つめていても、顧客とのつながりを築くことはできません。
購入の瞬間ではなく、その前後を含めた購入に連なるステップにこそ、マーケティングの重要性があります。
点ではなく線の視点を持って、顧客時間に寄り添うことが必要です。
企業からすれば、顧客がたどる買い物行動のすべての段階に関与できることが理想となります。
「空間の壁」を越える
2つ目の要点は、「空間」です。
空間とは、そのチャネルの所在がオンラインかオフラインか、です。
ここまで述べてきた通り、顧客はオンラインかオフラインの店舗を選択して買い物をするのではなく、オンラインとオフラインを行ったり来たりしながら買い物をしています。
例えばデジタルカメラの購入を検討している消費者がいたとして、何の情報も持たずにいきなり店舗に行き、商品を購入する人はもはや少数派だと考えられます。
大半の消費者は購入前にネットで情報を検索し、そのままオンライン店舗で購入するかもしれないし、オフライン店舗で購入するかもしれません。
重要なのは、自社の強みであるチャネルを有効に活用し、顧客との繋がりをつくることです。
オンラインに強みがある企業なら、既存のオフラインに存在したチャネルを見直し、オンラインのチャネルへの投資に振り替えることも考えられます。
例えばパンフレットやチラシなどではなく、何らかのオンラインのチャネルに変更できれば、顧客が何を求めているかという選択段階の行動を知る手がかりが得られます。
お客様相談センターだけでなく、オンラインでのレビューなども分かれば、顧客の使用段階での率直な評価をさらに広範に知ることができます。
チャネルを「連携」させる
3つ目の要点は、「連携」です。
顧客体験を軸とした個々のチャネルの連携は、チャネル設計において最も重要です。
顧客時間に寄り添い、オンラインとオフラインの空間にチャネルを配置するだけでなく、それらが一体となってどんな「購買体験」をもたらすのかを、意思を持ったストーリーとして描き出すことが求められます。
したがって設計の段階で描くチャネルは、自社のコントロールが効くチャネルが中心になります。
ストーリーの「主役」は、あくまでも顧客です。
顧客がどのような購買体験を得られるのかが、デザインの軸になります。「良い体験」は、主人公である顧客を取り巻く時間の経過と空間(場面)によって形づくられる、という考え方です。
そして、ストーリーを描く「主体」は、あくまでも企業です。
チャネルを用意し、そこを辿ることによって得られる購買体験を主体的に描き、顧客に提案します。
不足しているチャネルがあれば、新たに開発することも含まれます。
最も重要なのは、顧客の周りにいくつものタッチポイントをつくるだけでなく、顧客が1つのチャネルから別のチャネルに移る時に、シームレスな経験を提供できるかどうかです。
オムニチャネルは顧客満足度を最大化する
顧客満足度を最大化するためには、オムニチャネル戦略の導入が不可欠です。
顧客の購買行動の理解、オムニチャネルマーケティングの目的・目標の設定、オムニサイクルモデルの活用などを行うことで、効果的に業務を最適化することができます。
したがって、企業は自社のビジネスを最適化するために、最も効果的な戦略を立てるために、オムニチャネルモデルをしっかりと理解する必要があります。
オムニチャネルの活用について更に詳しく知りたい場合は、是非お問い合わせください。